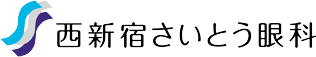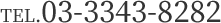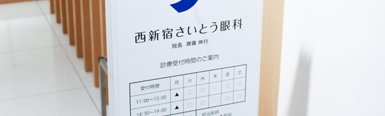お知らせ
糖尿病診察の流れ
2021年11月25日

糖尿病の患者さまは可能性を否定できない人まで入れると日本には約1370万人存在するとされています。また、50-60歳の糖尿病患者様のうち38.3%の割合で網膜症を合併しているとの報告があります。内科の先生と密接な関係をもち糖尿病の眼合併症の早期発見、早期治療が必要でしょう。
下記に内科の先生が行っている糖尿病診療についておおまかに記載いたしました。(糖尿病診療ミニマム)
初診時
1、『糖尿病連携手帳』(日本糖尿病協会)に必要事項を記載し患者様に渡す
2、既往歴・家族歴・20歳時の体重及び過去最大体重を確認
3、眼科紹介(糖尿病網膜症チェック)、歯科受診勧奨(歯周病チエック)
糖尿病における眼合併症は網膜症(30-40%)、白内障(60%)、角膜症(2%)、緑内障(1%)、眼筋麻痺(0.2%)、視神経症(0.1%)などがあります。
4、アキレス腱反射(糖尿病神経障害チェック)
5、尿定性検査(糖、タンパク、潜血、ケトン体)
6、食事の指示カロリー:(エネルギー摂取量)=標準体重×身体活動量を算出[標準体重(kg)=身長(m)二乗×22]
標準体重1kgあたりの身体活動量(必要カロリー)の目安25~30:ただし肥満を伴う場合25、肉体労働者等では35を推奨
7、体重測定・肥満度チェック=BMI(体重kg/身長(m)二乗 )25以上なら肥満、
18.5未満ならやせ
再診時
毎月
1体重測定 BMI 25以下目標
2 HbA1c 7未満目標 但し、高齢者のSU薬、インスリンの使用者においては8.5%未満を目標
3 血糖値 食後2時間値160mg/dl未満、空腹時130mg/dl未満目標
4 血圧測定 140/90mmHg未満目標
5 尿定性検査 糖、タンパク、潜血、ケトン体測定
6 禁煙指導 喫煙者には禁煙治療を勧奨
初診から3か月後までに
◆ 尿中アルブミン検査 糖尿病早期腎症の早期発見のため
3カ月毎に行うことを推奨
◆ 血液検査 Cr、BUN、尿酸、中性脂肪、LDL-C、HDL-C、AST、ALT、γ-GT
その他推奨される検査
1 眼底検査 眼底検査の間隔は糖尿病網膜症の状態により異なります。
網膜症がない場合は6~12か月に1回
単純網膜症の場合は3~6か月に1回
増殖前網膜症の場合は1~ 2か月に1回
増殖網膜症の場合は2週間~1か月に1回
上記は精密眼底検査の大まかな目安です。日常診療の受診期間は各人により網膜症の進行状態がことなるので主治医の先生の指示どうり通院しましょう。
2 足のチェク 爪白癬チェック、足背動脈触知
3 尿中アルブミン検査 糖尿病早期腎症早期発見のため
4 歯周病チェック
患者様がなすべき行動
1、症状がなくても月1回内科を受診、毎回採血
2、朝、昼、夕食を規則正しく、間食は控えめ、夜食はしない
・食べる順番は先ず野菜から(イモ類は野菜というより「ご飯」の仲間)、炭水化物は最後に
・「ゆっくり、よく噛み、腹八分目」
・食物繊維(葉野菜、海藻、こんにやく、キノコ)はたっぷり食べる
・おかずとご飯類をバランス良く(糖質制限は要相談)
・塩分摂り過ぎ要注意(1日の食塩:男性8g,女性7gまで、参考:ラーメン1食の食塩は約5g)
・くだもの食べ過ぎ要注意
・アルコール飲み過ぎ要注意、原則は禁酒、飲むなら1日25gまで(薬物療法中は要相談)
目安:ビールなら大瓶1本、日本酒なら1合、ワインならグラス2杯、ウイスキーならwで1杯、焼酎なら水割り1杯まで
・とにかくよく歩く(プラス10分多く、プラス10cm歩幅を広く)
以上が内科診療の大まかなながれです。
糖尿病網膜症は失明原因の2位になっており内科の先生に早期から適切な治療を受け患者様も努力して網膜が発症したり進行しないように努めましょう。そして繰り返しになりますが眼科にも前述したように受診して定期的な眼底検査を受けましょう。